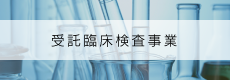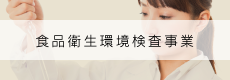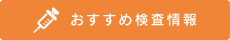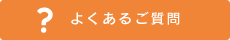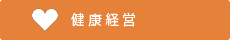このページ以降は、医療従事者の方へ情報提供することを目的としております。
一般の方へ情報提供をするものではありませんので、ご了承ください。
- Q、 血清カリウムが高いことが多い。
- Q、血糖用容器にて採血しなかった、生化学容器(血清)で検査できますか?
- Q、「血小板凝集あり」とコメントがありました。
- Q、施設によって基準値の違うものがありますが、どのように解釈すればよしいでしょうか?
Q、 血清カリウムが高いことが多い。
A、カリウムは細胞内(血球)に大量に含まれ、細胞外液(血清)中には少量しか存在しません。採血後、全血のままで放置すると血球内から血清中に漏出して異常高値となります。この傾向は冷蔵保存した場合に顕著であるため、血清K値を検査するときは低温での全血保存は禁忌です。特に冬季は室温が低下するため注意が必要です。採血後は温度変化の少ない場所にて保管頂くことをお勧めします。また可能であれば血清分離頂く事をお勧めします。
Q、血糖用容器にて採血しなかった、生化学容器(血清)で検査できますか?
A、検査できません。採血後でも血液中の細胞(赤血球、白血球、血小板)は血中のグルコースを消費してエネルギーを得ているため、全血のまま放置すればグルコースは低下します、低下の程度は検体により様々なため測定しても患者様の血糖値を反映しているとは言えません。血糖用容器はこれを妨げるために解糖阻止剤が入っています。
また、グリコアルブミンは、約2週間前までの平均血糖値を反映し、生化学容器(血清)で実施できます。
Q、「血小板凝集あり」とコメントがありました。
A、血液塗抹標本を顕鏡し血小板凝集がありました。血液分析装置からの情報で血小板凝集が疑われた場合、血小板数が11.0未満の検体、白血球数が20,000以上或いは2,000未満の検体は全て血液塗抹標本を作製し顕鏡確認します、その際に測定値に影響を及ぼす規模の血小板凝集が確認された場合にコメントを付記します。血小板凝集はEDTA依存性場合が多いため通常のEDTAに加え血小板用としてクエン酸Na管による採血をおすすめしております。弊社から提供することはできませんが、EDTA管にカナマイシンを添加したものも用いる病院様も多いようです。
Q、施設によって基準値の違うものがありますが、どのように解釈すればよしいでしょうか?
A、基準値には主に所謂健常者をサンプリングし95%の人がその内に入る基準範囲と、学会等で定める臨床判断値、特定健診等で設定されている予防医学的閾値(基準値)があります、弊社では基本的には基準範囲を、またはA1cや血糖等のようにガイドライン等で臨床判断値が明確なものはそれを採用しております。一般的な生化学的検査や血算につきましては、検査実施施設間差は現状少ない状況です。詳しくは弊社営業へ申し付けくだされば個別にご説明いたします。